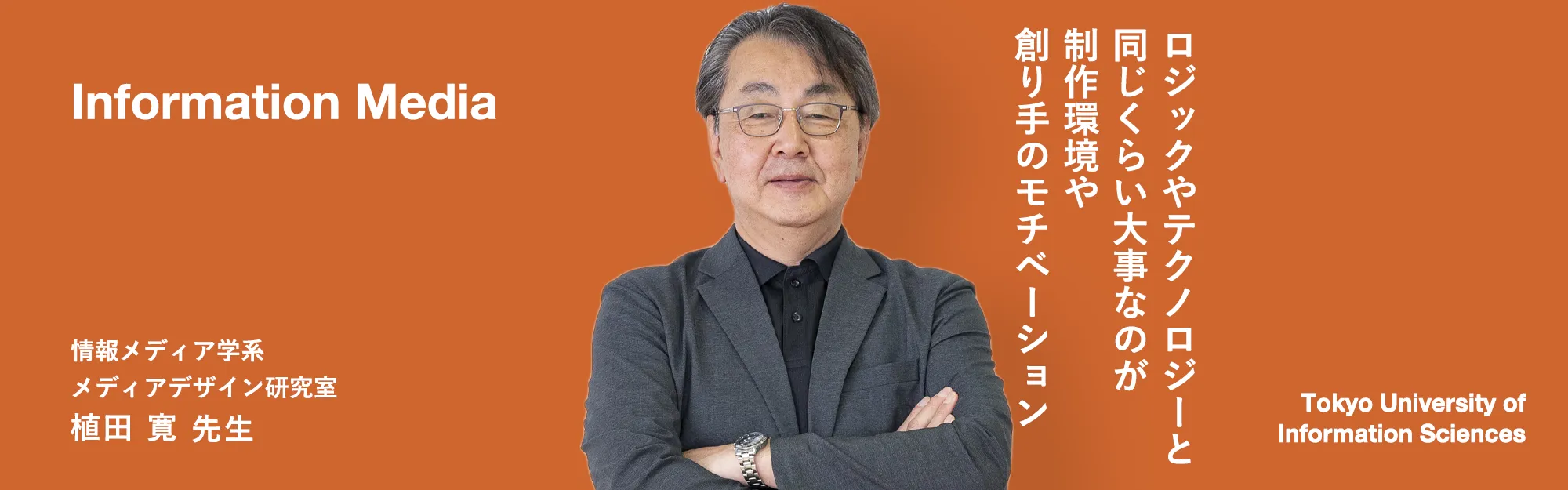
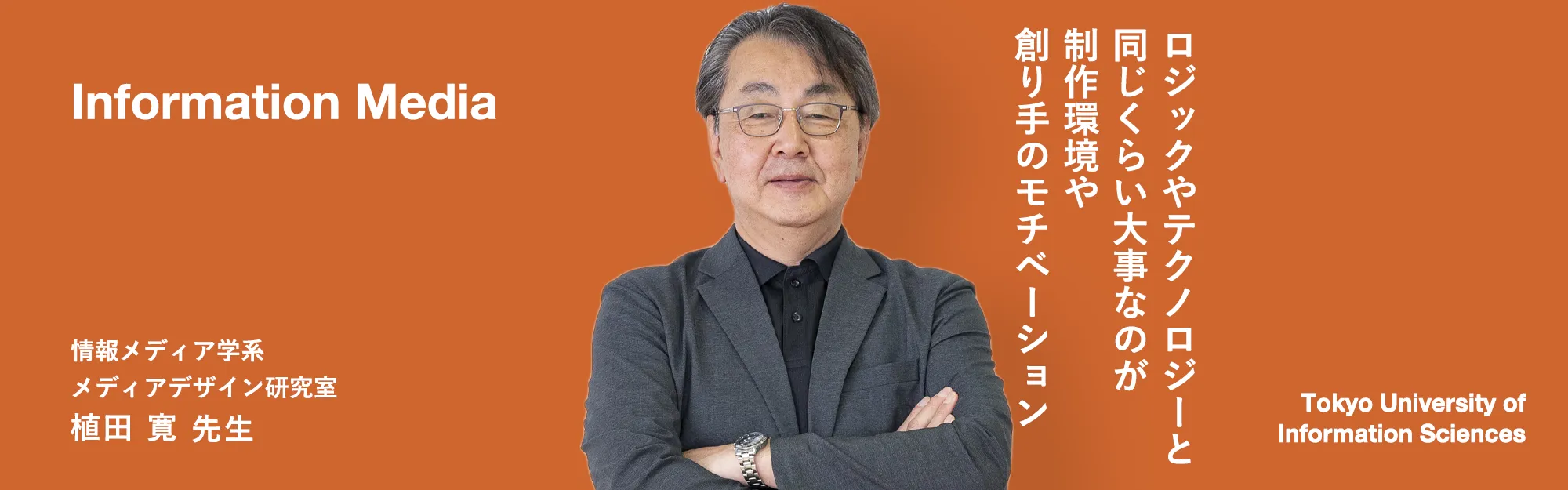
テレビは、決して難しい顔をして見るものではなく、食事をしながら、あるいは家族団欒の延長でつけたままだったり、なんとなくスマホいじりのBGM的につけているような、『ながら見』をしている人が多いのではないだろうか? 「それ以前に、そもそもテレビをあまり見ずに、もっぱらスマホやインターネットを見ている方もいるのでは?」と語りかけるのは植田寛先生だ。
「実は皆さんの世代の少し前より、大きくメディアが変貌しています。特に『映像』に関わるメディアは、大きく変貌を遂げようとしています。その過渡期に皆さんはいるのです」
マスコミ(mass communication)という言葉は、本来「大衆のコミュニケーション」という意味だが、少し前の時代までは、力のあるメディアが一方的なベクトルで大衆に情報を送りつけていて、相互コミュニケーションではなかった。それが、インターネットの登場により、現在ではようやく、より個人の情報の発信が実現している。本来の意味に近づいたともいえるだろう。
「YouTuberが小学生の人気の職業にランクインしているのも、その辺りも踏まえた新たな時代の幕開けなのかもしれません」と植田先生は話す。

「そんな寝っ転がったりしながら『ながら見』されがちなテレビのドラマや、映画のストーリーは、なぜ見ている人に理解できるのでしょうか? 起こった事象順に整然と編集されたものばかりではなく、夕食の直後に、場面が翌朝に急展開していることなどドラマの中ではよくあることです。あるいは回想シーンとして過去を振り返る事もあるわけです。つまりカメラ自体は時間を超越し、空間を瞬間移動しているにも関わらず、ほとんどの場合、シーンの展開に混乱なく解釈を行い、多くの人は『次の日のことだ』『過去のことだ』と理解している訳です」と植田先生は問いかける。なぜ私たちは理解できるのだろうか?
「実は『映像表現』を学ぶ際は、そこまで理解する必要があるのです。詳細は授業で触れていきますが、なかなかアカデミックな話になってきます。私自身はその辺りはC. メッツの『詩的映像』という考えに大きく影響を受けました」
こうした話は、「映像記号論」というもので、植田先生の授業で学んでいくことができる。
「それでは、映像制作とはそのようなアカデミックな考えに裏付けされたテクニックによって表現を綴るものであるかと言えば、少し異なります」
映像制作の現場でのイロハは「アゴ(=食事)、アシ(=交通手段)、マクラ(=宿泊)」と言われている。直接映像制作には関係ないようだが、基本中の基本とされており、ロケ(撮影)での作品クオリティを担保する必須条件となっている。
「テクニックやロジック、テクノロジーが大事であるのと同様に、制作環境を整えること、そして制作者のモチベーションを保つことも重要です。東京大学が開発した『EizoWorks(制作工程管理ソフトウェア)』でもその点が重視されていました。そこまでくると結局のところ映像制作とは一体何か? わけがわからなくなるかもしれませんが、そういったものなのです」
そのため、何も考えなくても撮ってしまえば作品になると考える人もいるのだという。
「もっと言うと、A Iを利用した動画生成システムで、短絡的に映像を提示して自分の作品だと言っている方も存在します。その一方で、その反対側にはなかなか深い蘊蓄をはらんだものと考えられるのです」
ここまで読んで映像制作に興味が湧いた人は、植田先生の授業でその蘊蓄に触れてみてはいかがだろうか?
